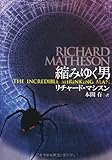第377話/ヤクザくん24
ひとりでことをおさめて丸儲けしようとした熊倉だったが、ハブの覚悟と危険性を見誤り、子分を射殺、自身も足をうたれ、あっさり捕縛されてしまった。
ハブたちは最上を男優としてAVを撮影するつもりのようだが、それが終わったのかどうなのかよくわからないところで、マサルに肉蝮から電話がかかってくる。肉蝮が非常に厄介な男だということはマサルもわかっている。いちおう、当ブログではマサルがのちのちのことを考えて、生き残ったヤクザと肉蝮をぶつけてつぶしあわせることで漁夫の利を得ようとしているのではないか、と想像してきたが、とりあえずいまのところは接触して後悔しているところが大きいのではないだろうか。会話が成り立たないうえに作中最強人物だもん、誰だってかかわりたくないだろう。喧嘩になっても屈服すれば見逃してくれる範馬勇次郎のほうがまだマシである。
流れとしては、ハブがあっさり熊倉の部下を殺したらしいところと、これから熊倉が最上に犯される(あるいはすでに犯されている?)ところを見たばかりで、もともと脳裏にあった「やるといったらやる」男であるところのハブのリアリティを直接体験したばかりである。現場にいたら、電話の向こうの肉蝮とハブのどちらがヤバイかといわれても窮するかもしれない。それに、すぐそばには獏木がいる。獏木はマサルが肉蝮と通じていることを知らない。そればかりか、肉蝮に右目をつぶされた獏木は彼を殺したいとおもっているし、しかもそのことはマサルに話してあるのである。獏木のために探りを入れている、等の言い訳をしても、たぶん通らないだろう。
というわけでマサルは電話に出ない。というか出れない。地元の友達からの電話だ(だから出なくていい)、と露骨に動揺しながらマサルがいうのを獏木が疑わしげに見ている。獏木のほうでもマサルに隠し事があるようだし、まあ信用はしていないのだろう。だけどまさか肉蝮と通じているとはおもっていないだろうな。
マサルが電話に出ないので肉蝮は激おこである。電話に出れないことなんてふつうにあるとおもうが、そういうのは通用しない。聞く耳もたねーなら両耳ちぎって逆向きにつけてやる、などと実に肉蝮らしいメッセージがマサルに届く。
どこかのコンビニの前にあぐらをかいてご飯を食べているヤンキーふたりが、いきがって一般人をからかっている。見るからにウシジマワールドでは小物風だが、まあふつうのひとは関わりたくない。亀田と鴨川というふたりである。
帽子をかぶったほうの鴨川がタバコを買いにいったんコンビニのなかに入る。ひとりカップラーメンが完成するのを待つ亀田のところに、肉蝮がやってくる。金かしてくんねーと。亀田はとりあえず肉蝮の巨大さにびっくりして動揺する、が、いちおうこうして不良をやっているわけで、引くわけにもいかない。ひとりでカツアゲする気か、こっちはふたりいるんだぞと、たぶん自覚はないだろうが、じぶんひとりでは無理っぽいということをすでに認めてしまっている。
肉蝮は亀田のことばをまるで聞いていない。ふつうに腹がへってコンビニにきたけど、手持ちがない、みたいなことかもしれない。肉蝮なら、ふだん財布を持ち歩かず、そこらへんのひとから集めて毎日過ごしている、といわれても驚かない。で、コンビニにきたらおあつらえむきの、すぐに警察に走ったりはしないワルそうなのがいたのである。肉蝮には彼らが財布に見えるのである。
肉蝮は亀田の前でまだできていないカップラーメンを勝手に食べ始める。「まだ硬いな」って、そりゃいまつくってるところだからね。ちゃんと後入れのかやくとかいれたんだろうか。
ラーメンを食われたことじたいは笑っちゃうくらいどうでもいいことだけど、とりあえずこの男がじぶんをなめていることはまちがいない。亀田は引き下がれない。さらって山に埋めるぞ、知り合いのヤクザ呼んでやるという。定型文みたいな文句だが、いちおう、じっさいそういうことを頼めるヤクザの知り合いはいるらしい。いいけど、「勝手にカップラーメンを食べられたんです」っていうのかな・・・。ちょっとまぬけすぎないか。
肉蝮はそういう亀田にも、「誰?(誰を呼ぶのか?)」と、意外な応答をする。亀だのいっているヤクザとは最上のことだった。肉蝮は知らないといいつつ、わりばしの袋のなかに入っていた爪楊枝をなんの躊躇もなく亀田の左目に突き立てる。黒目のとこの真ん中にモロにぶっささっている。
絶叫する亀田の左目に今度はスプーンをあてがい、黙らないと目玉えぐりだすぞと脅す。今すぐATMで全財産おろしてこいと。
殴られて歯が折れたとかくらいならまだ冷静でいられたかもしれない。しかし目の真ん中に爪楊枝とは、もうあたまがパチパチしてなんにも考えられなくなるんじゃないか。亀田は素直に応じてATMに行くが、店内の鴨川に状況を伝えて、最上を呼んでくれと頼む。しかし、店のなかから外にいる肉蝮を確認した鴨川は表情を変える。お前はあいつを知らないのかと。最上ではとてもかなわない。そうして、鴨川のくちから肉蝮のことが語られる。刑務所に入るたびに全国のヤクザから手紙や差し入れが届くのだが、それが中で組員をイジメないでくれということらしいのである。強盗殺人をしたことがある、というのは以前加納のくちから語られたことがあるが、さらに都市伝説的なうわさとして揉めたヤクザを殺して、刺青から身元がバレないように全身の皮を剥いで山に捨てたことがあるらしい、ということも語られる。ここで絵が描かれているので、このはなしはたぶんほんとうなんだろう。森のなかに転がる死体は、遠いので細かいところはわからないが、ほんとうに手や足の先以外のすべての皮が剥がれているっぽい。さらに、指も全部切り落とされ、歯も抜かれている。これではもうすぐ発見されたとしてもだれだかわからない。そして、なぜか胴体も切断されている。足首にはロープがまかれているが、まさかプレデターみたいに逆さに吊るして血をぬいたんだろうか。内臓は転がる死体の、その切断面に散らばっているので、死体がこの状態のときに胴体は切断されたらしい。村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』で生きたまま皮を剥がれる描写があったが、あのときはたいへんな出血量だった。すでに死んでいる状態で剥いだ場合、そんなに血は出ないんだろうか。いずれにしても、皮を剥ぐことで出た血はいっさい見当たらない。たぶん、なんらかの方法で殺したあと、吊るし、大体の血を抜いてそこから皮を剥ぎ、終わったところでおろして、なぜか胴体を切断したのである。あるいは、手術痕的や人工臓器的なものを消し去るためだったり、単純に胃の内容量から推定されないようにとか、そんなことかもしれないが、もうこれ以上はわからない。
ともかく、そのはなしがほんとかどうか不明だとしても、そうしたうわさが立つような人物ではあることはまちがいない。地元で敵なしの獏木だって目をつぶされたのだ、絶対かかわってはいけない人物だと鴨川は語る。たしかに、それじゃ最上なんか出てきたってなんにもできないだろう。いまの状況ではハブも丑嶋の件で手一杯で、仮に最上がやられてもじぶんでどうにかしろって感じだろうし。
裏口から逃げるとか、それでもとりあえず最上に連絡するとか、最後の手段として警察に電話するとか、いろいろあったとおもうが、ふたりはそのどれも選択しない。外から肉蝮がじっと見ていたのかもしれない。亀田はほんとうに全財産おろしてきた。いちどにそんなにおろせるものなのか、貧乏なので知らないが、とりあえず数十万から百万近くはある。亀田が素直に金をもってきたせいか、肉蝮はのんびりした調子に戻っている。そして、ひとりごとのようにmサルっていうダチが無視するからむしゃくしゃしていたとくちにする。鴨川はその名前を記憶する。そして、肉蝮がマサルと殺す約束をしていた人物が丑嶋だということも認識した。
ご機嫌になった肉蝮は三人を連れてゲーセンに行くことにする。亀田は病院にいきたがるが、彼はすっかり肉蝮に気に入られてしまった。無傷の鴨川は肉蝮に連れられながら、もう最上どころではないはなしなので、復讐の件もこみで、獏木に連絡するしかないかなどと考えているのだった。
つづく。
肉蝮が超人すぎる回であった。
鴨川はマサルという人間が肉蝮の友人で、ふたりは丑嶋を殺そうとしているということを認識した。この流れはまちがいなく、彼が獏木にそれを伝えるやつである。マサルという名前じたいはいくらでもあるので、それだけでは確定にはならないが、そこに丑嶋の名前までからんでくると、このマサルというのが加賀勝のであるということがほぼまちがいなくなってしまう。マサルにとっては非常に非常に、命の危機的な意味でまずい状況ではあるが、また大きくはなしが動いていくだろう。
もしマサルが肉蝮と通じていることを知ったら、獏木はどうするだろう。たぶん、いきなり怒り狂うということはないだろう。もともと彼はなにかを隠しているし、たんに利用しているだけというぶぶんは大きいはずだ。しかし肉蝮の件はハブたちとは無関係の、個人的な問題である。もしかしたらひとりでどうにかしようとするかもしれない。もしあの倉庫に呼び出すような事態になったら、こりゃもうとんでもないことになる。丑嶋・滑皮組も、戌亥の働きで現場を知りつつあるのだ。最大トーナメントでも開けそうなくらいの、作中の強者が集合してしまうことになるのだ。
今回は、肉蝮が獏木レベルではない、筋金入りのヤクザと接したときどう出るのか、ということのこたえが出た。別にいつもと変わらないのである。
鴨川が語るエピソードもいかにも都市伝説的で、ほんとかよって感じだが、もし本当のことだとしたら、どういうことになるだろう。肉蝮がいったいいくつくらいなのか不明だが、刑務所にいる彼に(そもそも捕まったことがあるというのが驚きだが)ヤクザたちが差し入れをするということは、これまでもそうしなければどうしようもないような状況になったことがあるということだ。鴨川の言い方では肉蝮は何度も服役していたことがあるっぽい。それが、彼の丑嶋襲撃計画が遅々としていた理由かもしれない。まあすぐ出てきているわけだから、殺人とかではなく、もっと軽い罪ではあるのだろう。で、肉蝮はヤクザを全然恐れないので、出所してから復讐されるとかそんなことは全然気にせず、刑務所でなんか威張っている気に入らないやつをイジめるのだ。そして、もしかすると、そのことで出所後復讐しようとしたヤクザを返り討ちにしたことがあるのではないか。ヤクザとしては、ハブがいまそうしているように、面子をどう立てるかということが最重要になる。いくら肉蝮でも、ヤクザではないという意味ではカタギなわけであるから、本来であるならなんとしてもその復讐をしなければならないはずである。が、ヤクザたちはそれをしないばかりか、差し入れをしてご機嫌をとる。ということは、面子をかけて殺しにいくリスクよりも、適当にご機嫌をとっておいたほうがコスト・パフォーマンスがよいととらえていると考えるほかない。こういうはなしは大げさに伝わるので、たとえば「全国の」とかいうぶぶんは若干誇張である可能性もある。肉蝮は年中今週みたいなカツアゲをしているから、たぶんしょっちゅう捕まっている。で、逆に考えると、刑務所内では銃などの武器はない。あれほどの超人であるから、たぶんふつうのヤクザでは束になってもかなわない。刑務所内で「復讐」をすることはできない。では外にいるときにやろうとしても、それはそれでいろいろ面倒なのである。いくら肉蝮でも殺せば犯罪だし、あんな巨人なのだからこちらも無傷とはいかない。そして家がないかの如くいつもうろうろ歩き回っていて神出鬼没、どこにいるかわからず、そして放っておけばすぐ捕まる。そうしたなかで、面倒に感じたヤクザが差し入れなどを行ったとき、それを知ったほかのヤクザが同様のことをまねしようと考えたとしても不思議ではない。誰でもやっていることで、常識的なことであるなら、それで面子がつぶれるということはないからである。じっさいに刑務所でいじめられたヤクザの自尊心は傷つくかもしれないが、それだからといって若い衆の死者を出すかもしれない覚悟で別にヤクザでもなんでもない肉蝮に返しをするのもなんか割りに合わない。そんな感じで、いつのまにか業界で「肉蝮については触れない方向で」みたいな合意形成がされたのではないだろうか。
いずれにしても、肉蝮の神話的強さは物語を大きく動かすことになる。なぜなら、主人公の丑嶋にしてからが、「ヤクザには逆らってはいけない」という原理から逃れられてはいないからである。それをやってしまったから、いま丑嶋はこんな目にあっている。彼らの生きる裏社会で、ヤクザくんというのは、重力のような自然界の法則や、あるいは数学でいうところの公理(根本命題)みたいなものなのである。ハブにも滑皮にも丑嶋にもマサルにも、立ち位置というものがある。社会的価値と言い換えてもよい。人間関係においての、じぶんの占めている面積や形状のことである。ヤクザは基本的に面子(他者のイメージするわたし)を第一に行動するが、なかでもハブはいまそれに突き動かされるかたちになっている。滑皮は滑皮で、後輩たちにとっての「かっこいい先輩」を演じるためだとか、それと同形の行動として熊倉を立てたりだとか、ひいてはヤクザ業界を賦活するためだとかいうふうにして、組織に生きている。丑嶋も、ハブを殴ってしまったとはいえ、やはり滑皮には逆らえないし、その構造そのものを憎みつつも、滑皮と共闘しようとするかのような姿勢で雌伏に甘んじている。マサルでは現状ハブ組とのかかわりが大きいが、そもそもはカウカウでの社長との関係性ということがある。しかし肉蝮にはそういう、行動の足元に描かれているべき根本的な動線のようなものがまったく欠けている。丑嶋がヤクザを憎むときも、マサルが打倒丑嶋を願うときも、滑皮が旧式のヤクザスタイルを重んじるときも、ハブが面子を気にするときも、必ず、回復したり、覆したりしようとされるモデルや地図のようなものがある。それが肉蝮にはない。完全に自由なのである。
だから、もし今後肉蝮がヤクザと衝突することになっても、そこではたとえば「ヤクザを殴ってはいけない」というような当たり前の前提はまったく通用しない。つまり、肉蝮の前では「ヤクザくん」という社会的価値が全然意味をもたないのである。彼の前では、「ヤクザくん」というものが存在することができないのだ。いや、ヤクザだけに限らないかもしれない。闇金ウシジマくんはこれまで数え切れないほどのたくさんの「社会的価値」を描出してきた。それは要するに、生き方の差異のことであった。世界にはいろんな人間がいて、いろんな生き方をしている。その生き方の一般化が、通常職業の名前で代替される「××くん」という副題なのであった。しかし、どのような「××くん」も、すべてそれ以外の「○○くん」との差異によって成立してきたのである。フーゾクくんがホストくんをホストくんたらしめ、ヤンキーくんがフリーエージェントくんをそれたらしめる・・・という具合に、わたしたちは、「わたしたちとはちがう生き方をしているもの」との差異によって、わたしたちの生き方を言語化し、一般化することができる。それが、わたしとわたしではないものとしての無数の他者との関係が作り出す「社会」というものである。裏社会のヤクザやヤンキーであってもそれは変わらない。むしろ、裏社会ではヤクザがすべてを統一的に秩序立てるぶん、そうした関係性は強固かもしれない。しかし、自由人・肉蝮の前ではそうした価値はなんの意味ももたない。彼は、わたしたちが生きていくうえで自然と着込むことになるエクリチュール(文体)を剥ぎ取り、生身のまま接することを要求してくる唯一の人物だったのである。
そんな肉蝮がもっとも殺した人物、それが丑嶋である。ギャル汚くんで肉蝮は丑嶋に負けているのである。ただ、あの勝負はカウカウメンバーのチームワークによるところが大きかった。つまり、負けてもしかたがなかったというぶぶんがかなりあったのである。それにもかかわらず、肉蝮はハブのように「カウカウ」を皆殺しにしようとはしない。というのは、彼の復讐心が「負けたこと」によって燃やされているわけではないからだろう。肉蝮は相手の社会的価値を剥ぎ取り、生身での対決を要求してくる。そして彼はあのとき丑嶋に、同じことを逆にやられたのだ。生身どうしの対決になれば、ヤクザであっても肉蝮あからすれば弱々しい存在である。しかし丑嶋は、みずから価値を脱ぎ捨てるようにしてすすんで生身になり、からだいっぱいの殺意のこもった目つきで包丁をつきつけたのである。そして、そこで肉蝮は降参してしまった。彼を突き動かすのはこのときの記憶である。構造的意味でも、肉体的意味でも、生身の状況は彼の領域である。彼はそこで負けたのだ。
- 闇金ウシジマくん 34 (ビッグコミックス)/小学館
![]()
- ¥596
- Amazon.co.jp
- 闇金ウシジマくん 33 (ビッグコミックス)/小学館
![]()
- ¥596
- Amazon.co.jp
- 闇金ウシジマくん 1 (ビッグコミックス)/小学館
![]()
- ¥545
- Amazon.co.jp